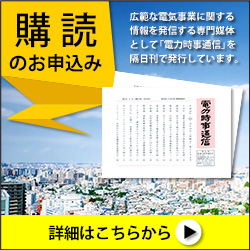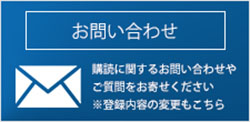電取委 来年度以降の需給調整市場監視見直し
電力・ガス取引監視等委員会は、需給調整市場の監視について見直す方針を示した。同市場は、21年度に開設して以降、段階的に商品を拡充し、昨年度から全商品の取扱いを開始。今年度は三次調整力②が30分取り引きに移行した。
さらに来年度以降は、全商品前日取り引き化・30分取り引き化となり、市場環境の変化が生じる見通し。同市場に対する監視の在り方を検討する同委は、20年12月に「需給調整市場において適正な取引を確保するための措置について」を取りまとめ、翌21年3月には「適正な電力取引についての指針」(適取GL)を改定すると共に、「需給調整市場GL」を策定。これらに基づくこれまでの取り組みを踏まえ、来年度以降の監視と価格規律の在り方を検討した。
現行の施策では、同市場において、適正な取り引きを確保するための措置として、全ての事業者に対し、事後的措置を適用する。事後的措置に違反した場合は、業務改善命令などの対象とし、同措置の具体的なケースを適取GLに提示。大きな市場支配力を有する事業者には、事後的措置に加えて、競争的な市場において合理的な行動となる価格で入札(登録)することを求める事前的措置を設けて、遵守するよう要請する。同措置の詳細を規定する需給調整市場GLでは、24年度以降、調整力提供事業者からの申請により、Δ㎾価格の内訳の「一定額」を、電取委事務局と協議して決定する、B種電源の仕組みを導入・運用している。
同協議については、24年度5件(電源3件、蓄電池VPP2件)、25年度(10月17日時点)34件(電源28件、蓄電池1件、蓄電池VPP5件)を実施。申請内容に関して、非常に多くの項目を確認する中で、合理的に説明できない費用などについて、協議の妥結点を見出すため、申請事業者と電取委事務局双方に多くの事務的・時間的負担が発生するなどの課題が挙がっている。上限価格や募集量の削減策が講じられた現在の市況では、協議額では約定し得ない状況で、B種電源協議自体の有用性に疑問が生じている。
これらの課題を踏まえて電取委は、B種電源協議を26年度以降廃止すると共に、需給調整市場GLに規定する、Δ㎾価格の考え方について、応札事業者が価格規律を遵守した価格設定を円滑に行えるよう明確化した上で、同GLの主旨に則った算定方法とする考えを示した。
事後的措置として適取GLで規定する「同市場で問題となる行為」については、26年度以降は、同市場GLに具体的な処分対象行為を追記する。監視の実績や同市場の運用状況を踏まえて、〇不合理な入札価格(登録価格)・入札量の設定により、不当に収益を得る行為、〇不適切なシステム設定により、不合理な入札価格(登録価格)・入札量が設定され、需給調整市場やインバランス料金の精算に関して、他の複数の事業者に影響を与える行為―を問題となる行為に加える。