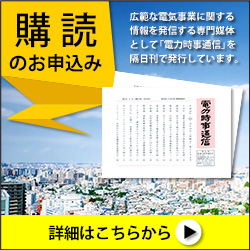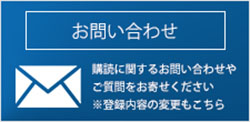ATENA 太陽フレアへの新たな警報基準
原子力エネルギー協議会(ATENA)は、太陽活動による通信連絡設備などへの影響が懸念されることから、情報通信研究機構(NICT)による「社会的影響を考慮した新たな予報・警報基準」の整備状況を踏まえて、原子力事業者における対応体制を強化する。
太陽の表面で突然発生する強力な爆発現象「太陽フレア」についてNICTは、同予報・警戒基準を設定し、今月からの運用開始を予定しており、ATENAは今年2月から、原子力発電所の通信連絡設備における警戒レベルの設定、原子力事業者の体制強化などについて、電力9社、日本原電、Jパワー、日本原燃と共に、太陽フレアWGを設置して検討を進めてきた。
太陽フレアなどにより、具体的に影響を受ける可能性がある、通信連絡設備などを整理し、具体的影響が顕在化した場合でも、太陽フレアなどの影響を受けない代替措置が備わっていることを確認。発電所の運転継続は可能―との判断を示した。その上で、NICTの新たな警報基準と実績の対比、NICTが提供する「宇宙天気予報」の発信状況などを踏まえて、原子力における通信連絡設備の警戒レベルを定め、そのレベルに到達した場合は、警戒態勢を敷くことで、太陽フレアなどによる影響を受けない、通信連絡設備を確実に使用できる体制を強化する考えを示した。
具体的には、NICTから太陽フレア警報、またはプロトン警報が発信された場合に、警戒態勢を整える。警報発信から3日間は警戒態勢を維持し、コロナガスの放出といった後続事象への対応を可能とする。維持期間に新たな警報が発信された場合は、その時点から3日間警戒態勢を維持する。各原子力事業者に対して、これらの原子力における新たな警報基準を踏まえて、〇警報配信時の対応態勢の確立、〇太陽フレアなどにより影響を受ける可能性のある、通信連絡設備などと代替措置の確定、〇警戒態勢時の対応の手順確立(手順書への反映)―をこのほど要求した。
同要求を受けて事業者は今後、2か月を目途に対応を準備。今年は太陽活動の極大期にあたり、同時期が経過した後、NICT警報発信状況や通信連絡設備などへの影響を確認する。警戒態勢の運用は、必要に応じて適宜見直す。